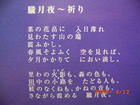おだほしぶろぐ - 最新エントリー
先日、映画「剱岳 点の記」を観ました。
明治末期に、地図上で最後の空白地となっていた剱岳周辺の地図を
作るために、周辺山岳に三角点を設置し測量をするお話です。
当然、前人未踏と言われていた岩峰の剱岳にも登らなくては測量は
できません。
一方では、当時結成したばかりの日本山岳会も剱岳初登頂を目指して
おり、測量隊(陸軍測量部です)としては、陸軍の面目にかけても先に
登らなくてはならない。
しかし、仕事(測量)には順番があるので、困難で時間もかかる
剱岳登頂ばかりを優先するわけにはいきません。
測量をしている脇を、山岳会が進んでいくところを複雑な心境で
見送るシーンなどは「戦う観測者」が重なりました。
三脚を立てて機材を扱って計測するところは、天体観測と同じですね。
原作は新田次郎の山岳小説。
淡々と、しかし情熱的に責任感を持って仕事を進める様子が描かれ
ています。
地味な作品でしたが、いろいろと考えるところがあり良い映画でした。
山岳風景の映像は見事でした。
映画パンフレットなので詳しく画像掲載できないのが残念です。
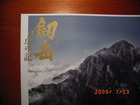
明治末期に、地図上で最後の空白地となっていた剱岳周辺の地図を
作るために、周辺山岳に三角点を設置し測量をするお話です。
当然、前人未踏と言われていた岩峰の剱岳にも登らなくては測量は
できません。
一方では、当時結成したばかりの日本山岳会も剱岳初登頂を目指して
おり、測量隊(陸軍測量部です)としては、陸軍の面目にかけても先に
登らなくてはならない。
しかし、仕事(測量)には順番があるので、困難で時間もかかる
剱岳登頂ばかりを優先するわけにはいきません。
測量をしている脇を、山岳会が進んでいくところを複雑な心境で
見送るシーンなどは「戦う観測者」が重なりました。
三脚を立てて機材を扱って計測するところは、天体観測と同じですね。
原作は新田次郎の山岳小説。
淡々と、しかし情熱的に責任感を持って仕事を進める様子が描かれ
ています。
地味な作品でしたが、いろいろと考えるところがあり良い映画でした。
山岳風景の映像は見事でした。
映画パンフレットなので詳しく画像掲載できないのが残念です。
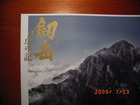
今日は爽やかな快晴!
・・・のはずなのですが、これは箱根雲です。
頭上から東は晴れています。
太陽が箱根雲にかかる前にスケッチをしました。
・・・のはずなのですが、これは箱根雲です。
頭上から東は晴れています。
太陽が箱根雲にかかる前にスケッチをしました。
このところ大気が安定していて土星がきれいに見えます。
環がかなり薄くなっているので、安定した大気でないと
見にくい状態なので、このちょっとよどんだような春の
大気はかえって幸いです。
さらに、今は南中が20時頃ですが、6月夏至の頃には
南中は16時頃となり、日没との兼ね合いでようやく観察が
出来る20時には西の低空へと移動してしまいます。
そんなわけで、土星を良い状態で見るにはここ1ヶ月位
のようです。
8月の環の消失時は、夕焼け空に低空で、実際にはとても
見づらいと思います。
環がかなり薄くなっているので、安定した大気でないと
見にくい状態なので、このちょっとよどんだような春の
大気はかえって幸いです。
さらに、今は南中が20時頃ですが、6月夏至の頃には
南中は16時頃となり、日没との兼ね合いでようやく観察が
出来る20時には西の低空へと移動してしまいます。
そんなわけで、土星を良い状態で見るにはここ1ヶ月位
のようです。
8月の環の消失時は、夕焼け空に低空で、実際にはとても
見づらいと思います。
今年の桜はかなりがんばって長い期間咲いていました。
その分、散り際は良かったようで、葉桜期間が短く一気に新緑となりました。
いろいろな所の桜を見てると、街の桜は見事なことに気が付きます。
同じソメイヨシノでも、郊外の木に比べ、街中の木は花の量がとても多いです。
ラジオ番組の桜特集で、弘前城公園の管理者のインタビューがあって、「桜は手間をかければかけただけ答えてくれる」と言っていました。
返して言えば、手間をかけないと衰える木でもあるわけです。
弘前城公園は「全国一」のプライドにかけて、市民上げてかなりの手間をかけているそうです。
桜の花は芽枝先にいくつかの花が集まって咲くそうですが、その集まりの数が、普通は5〜7程度らしいのですが、弘前のものは10〜11もあるそうです。
さらにひとつの小枝の花群の密度がかなり多く、これが枝も見えなくなるような開花にしているそうです。
確かに上野公園とか、小田原だったら城址公園の桜は見事です。
ソメイヨシノの花としての寿命は50年ほどらしいので、なにか人の一生にも重なるような気もします。
あの見事な桜はそれを育てる人の想いでもあったわけですね。
下の写真はどちらもソメイヨシノですが、先2枚は妙義さくらの里、後の2枚は妙義ふるさと美術館のものです。
開花状態が違うので直接比較は出来ませんが、花の付きや枝に付く花の量がかなり違います。
どちらも手入れされていますが、妙義さくらの里は自然公園なのでそんなには手を入れていないと思います。
美術館の方は写真スポットとして見せるために手を入れています。
花が多ければ良い、と言うものでもないので、どちらが好みかは人それぞれでしょう。
私は、妙義さくらの里のほうがいいかな。




その分、散り際は良かったようで、葉桜期間が短く一気に新緑となりました。
いろいろな所の桜を見てると、街の桜は見事なことに気が付きます。
同じソメイヨシノでも、郊外の木に比べ、街中の木は花の量がとても多いです。
ラジオ番組の桜特集で、弘前城公園の管理者のインタビューがあって、「桜は手間をかければかけただけ答えてくれる」と言っていました。
返して言えば、手間をかけないと衰える木でもあるわけです。
弘前城公園は「全国一」のプライドにかけて、市民上げてかなりの手間をかけているそうです。
桜の花は芽枝先にいくつかの花が集まって咲くそうですが、その集まりの数が、普通は5〜7程度らしいのですが、弘前のものは10〜11もあるそうです。
さらにひとつの小枝の花群の密度がかなり多く、これが枝も見えなくなるような開花にしているそうです。
確かに上野公園とか、小田原だったら城址公園の桜は見事です。
ソメイヨシノの花としての寿命は50年ほどらしいので、なにか人の一生にも重なるような気もします。
あの見事な桜はそれを育てる人の想いでもあったわけですね。
下の写真はどちらもソメイヨシノですが、先2枚は妙義さくらの里、後の2枚は妙義ふるさと美術館のものです。
開花状態が違うので直接比較は出来ませんが、花の付きや枝に付く花の量がかなり違います。
どちらも手入れされていますが、妙義さくらの里は自然公園なのでそんなには手を入れていないと思います。
美術館の方は写真スポットとして見せるために手を入れています。
花が多ければ良い、と言うものでもないので、どちらが好みかは人それぞれでしょう。
私は、妙義さくらの里のほうがいいかな。




このところ晴天続きで夏のような陽気が続いています。
先週は満月で「おぼろ月夜」の季節ですが、大気は乾燥
していて、意外とくっきりでちょっとそういうイメージは
ありませんでした。
昨日は満月2日過ぎのおぼろ月を夜桜と共に見ました。
なかなか風情があります。
その時ちょっと思ったのですが、唱歌「朧月夜」に
歌われている情景って、「桜が満開で、菜の花が咲いていて、
霞の中に満月が昇ってくる」風景が思い浮かばれる(らしい)
ようですが、実はどうなんでしょう。
昔むかし、音楽の授業で、その情景を歌でどう表現したのか
を習ったのは記憶があります。(記憶もおぼろ月のようですが)
今思うと、「もしかしたら満月ではなくて半月だったのでは
ないか」とか、「桜は関係ないのではないか」と考えたりします。
今の教科書にも、この歌載っているのでしょうか。
日本人ならぜひ知ってほしい歌です。
画像は、例会時に昇ってきた月を桜越しに撮りました。
夜景は大井町、「里わの火影」ってことになるのでしょうか。
歌詞は手元に無いので、中島美嘉さんの1曲、この歌の部分
の抜粋です。
この曲、「桜色舞うころ」のカップリングなんですよね。
やっぱり、桜とおぼろ月は離れないのでしょうか。



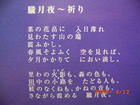
先週は満月で「おぼろ月夜」の季節ですが、大気は乾燥
していて、意外とくっきりでちょっとそういうイメージは
ありませんでした。
昨日は満月2日過ぎのおぼろ月を夜桜と共に見ました。
なかなか風情があります。
その時ちょっと思ったのですが、唱歌「朧月夜」に
歌われている情景って、「桜が満開で、菜の花が咲いていて、
霞の中に満月が昇ってくる」風景が思い浮かばれる(らしい)
ようですが、実はどうなんでしょう。
昔むかし、音楽の授業で、その情景を歌でどう表現したのか
を習ったのは記憶があります。(記憶もおぼろ月のようですが)
今思うと、「もしかしたら満月ではなくて半月だったのでは
ないか」とか、「桜は関係ないのではないか」と考えたりします。
今の教科書にも、この歌載っているのでしょうか。
日本人ならぜひ知ってほしい歌です。
画像は、例会時に昇ってきた月を桜越しに撮りました。
夜景は大井町、「里わの火影」ってことになるのでしょうか。
歌詞は手元に無いので、中島美嘉さんの1曲、この歌の部分
の抜粋です。
この曲、「桜色舞うころ」のカップリングなんですよね。
やっぱり、桜とおぼろ月は離れないのでしょうか。