冷却 CMOS CCD カメラ
- このフォーラムに新しいトピックを立てることはできません
- このフォーラムではゲスト投稿が禁止されています
投稿ツリー
-
 冷却 CMOS CCD カメラ
(k_kubotera, 2022/1/17 7:42)
冷却 CMOS CCD カメラ
(k_kubotera, 2022/1/17 7:42)
-
 Re: 冷却 CMOS CCD カメラ
(m_akashi, 2022/1/18 12:30)
Re: 冷却 CMOS CCD カメラ
(m_akashi, 2022/1/18 12:30)
-
 Re: 冷却 CMOS CCD カメラ
(k_kubotera, 2022/1/19 7:31)
Re: 冷却 CMOS CCD カメラ
(k_kubotera, 2022/1/19 7:31)
-
 Re: 冷却 CMOS CCD カメラ
(yomaiboshi, 2022/1/21 16:08)
Re: 冷却 CMOS CCD カメラ
(yomaiboshi, 2022/1/21 16:08)
-
 Re: 冷却 CMOS CCD カメラ
(nakanek, 2022/1/21 19:19)
Re: 冷却 CMOS CCD カメラ
(nakanek, 2022/1/21 19:19)
-
 Re: 冷却 CMOS CCD カメラ
(yomaiboshi, 2022/1/22 22:50)
Re: 冷却 CMOS CCD カメラ
(yomaiboshi, 2022/1/22 22:50)
-
 Re: 冷却 CMOS CCD カメラ
(m_akashi, 2022/1/23 9:33)
Re: 冷却 CMOS CCD カメラ
(m_akashi, 2022/1/23 9:33)
-
 Re: 冷却 CMOS CCD カメラ
(nakanek, 2022/1/23 10:24)
Re: 冷却 CMOS CCD カメラ
(nakanek, 2022/1/23 10:24)
-
 Re: 冷却 CMOS CCD カメラ
(yomaiboshi, 2022/1/24 23:29)
Re: 冷却 CMOS CCD カメラ
(yomaiboshi, 2022/1/24 23:29)
-
 Re: 冷却 CMOS CCD カメラ
(m_akashi, 2022/1/25 22:01)
Re: 冷却 CMOS CCD カメラ
(m_akashi, 2022/1/25 22:01)
k_kubotera
 投稿数: 4748
投稿数: 4748
 投稿数: 4748
投稿数: 4748
『未知変光星』のトピックの内容からずれそうなので、こちらに立て直しました。
私は詳しいことを知らないで冷却CCDを使っていますから、的はずれかもしれません。
変光星でも何でも同じと思いますが、どんな観測をするのかで機材を選びますから、今回は、購入するに機材でできる観測はどんな感じかなという方向でしょうか。
激変星の増光をいち早く捕らえるのであれば、一眼デジカメと画像をチェックする強力なソフトがあれば(赤道儀などの精度や自動化も必要とおもいますが)できるようです。
測光となると、いろいろと条件があります。
まず、カラーのカメラ、撮像素子の3つのピクセルが1つの組になってそれぞれにR,G,Bのフィルターがかかって撮像するので、フィルターの特性が、そもそも測光用と違いますから、厳密には国際的な標準のデータを使っての比較測光ができません。一眼デジカメなどから取り出したG画像から国際標準のV等級のデータを使って測光した値には、cGという記号をつけて区別することになっています。それでも、光度曲線を見る限りV等級のデータと大きく変わらないようです。
とはいうものの、撮像素子の分光特性も素子によって多少違いがあるので、それほど厳密なものではないようです。観測する星の明るさの振る舞いがわかればいいので、むしろ、撮影時や測光時の測定誤差をいかに少なくするかが大切みたいです。
カラーのカメラは3つのピクセルを1つの画素にするので解像度が落ちると天体写真の世界では言われるようですが、最近は画素数も多くなっているので、観測的には、問題ないと私は思います。むしろ、画像が重くなって転送や測光処理にそれなりのマシンスペックが必要になると思います。C-MOSは、CCDに比べて転送速度も転送時のノイズも小さいかもしれません。
ダイナミックレンジというか、銀塩フィルムでいうところのラチチュードが大きくないと測光の精度に関わります。一眼デジカメや冷却CMOSカメラは、どのくらいなんでしょうか。おそらく14ビットかもしれません。私の冷却CCDは古いですが、16ビットあります。たかだか2ビットの差ですが、4倍、測光では影響が出てくると思います。
ピクセルの大きさはため込む電荷の量や入ってくる光の量に関わるので、大きい方が感度いいし、飽和もしづらく階調も広くとれるでしょうか。解像度はやや落ちるのでしょうか、天体写真的なことはよくわかっていません。
ブルーミング(飽和)の問題、冷却カメラの仕様書には最近書かれていないことが多いです。撮像素子の最も大きな特徴は、直線的に電荷と光量の関係があることだと思います。強い光が当たれば、当然あふれ出しますが、本来はその状態を飽和と呼んでいましたが、今は、直線性を崩して、あふれ出ることを止めています。天体写真ではきれいに写っていいのですが、電荷を捨てる作業(画素にゲートを作って光を入れないようにしているのかな)をしています。直線性を崩すというのは、測光には致命的です。SOHOの画像で太陽のバックにある明るい星が飽和して横に電荷が流れ出ていたり、すばる望遠鏡の画像もそんなものがあったりします。あれはあれで、写っているものすべてが直線的に光量と比例している証拠です。
そんなこと言っていたら、NABG(ノンアンチブルーミング)以外のほとんどの素子が測光には不向きになってしまいます。そういう私の冷却CCDもブルーミング(飽和)を押さえる働きをします。
じゃあ、どうするかというと、電荷を捨て始める手前までを使っています。具体的には、機材にあった明るさの星を観測するとか、明るい星を観測する時は、ピントをぼかして1つの画素に入る光を分散させるとか、露光時間を調節するとか飽和させないような工夫をします。実際には勘と経験です。
でもそんなことして、いい加減なデータを報告すると叱られるので、測光の時に以下のようなことをしてどの程度の精度で測光できているのか調べておきます。

図は、測光で使うソフトの画面のひとつですが、左上のグラフ、画像に写っている星のほぼすべてがプロットされています。横軸は星の明るさ、縦軸は、測光値の標準偏差です。標準偏差が小さいところで測光している限り問題はありません。右側は暗い星で標準偏差は大きいですが、どの星も同じように標準編が大きいので、つまりばらつきは大きいけれど、平均値をとるとそれなりの光度曲線ができます。ところが、左の明るい星は、星によって標準偏差に違いがあり測光には向きません。適当に精度よく測光できるところに変光星や比較星を持っていくのが、先ほどの勘と経験です。帯状の分布から外れている星が変光星、または、変光が疑われる星です。
どこまで正しく理解できているかわかりませんが、測光には、まだ、いろいろな課題があったり、テクニック、知識が必要だったりで、終わりがありません。
ということで、カラー画像とモノクロ画像で違いが少しあるのですが、購入する機材と望遠鏡の組み合わせで、変光星の測光は可能と思います。画像の形式ですが、私は.ftsを使っています。他の形式の画像でも測光ソフトは動くようですが、使ったことがないので、なんともいえません。
私は詳しいことを知らないで冷却CCDを使っていますから、的はずれかもしれません。
変光星でも何でも同じと思いますが、どんな観測をするのかで機材を選びますから、今回は、購入するに機材でできる観測はどんな感じかなという方向でしょうか。
激変星の増光をいち早く捕らえるのであれば、一眼デジカメと画像をチェックする強力なソフトがあれば(赤道儀などの精度や自動化も必要とおもいますが)できるようです。
測光となると、いろいろと条件があります。
まず、カラーのカメラ、撮像素子の3つのピクセルが1つの組になってそれぞれにR,G,Bのフィルターがかかって撮像するので、フィルターの特性が、そもそも測光用と違いますから、厳密には国際的な標準のデータを使っての比較測光ができません。一眼デジカメなどから取り出したG画像から国際標準のV等級のデータを使って測光した値には、cGという記号をつけて区別することになっています。それでも、光度曲線を見る限りV等級のデータと大きく変わらないようです。
とはいうものの、撮像素子の分光特性も素子によって多少違いがあるので、それほど厳密なものではないようです。観測する星の明るさの振る舞いがわかればいいので、むしろ、撮影時や測光時の測定誤差をいかに少なくするかが大切みたいです。
カラーのカメラは3つのピクセルを1つの画素にするので解像度が落ちると天体写真の世界では言われるようですが、最近は画素数も多くなっているので、観測的には、問題ないと私は思います。むしろ、画像が重くなって転送や測光処理にそれなりのマシンスペックが必要になると思います。C-MOSは、CCDに比べて転送速度も転送時のノイズも小さいかもしれません。
ダイナミックレンジというか、銀塩フィルムでいうところのラチチュードが大きくないと測光の精度に関わります。一眼デジカメや冷却CMOSカメラは、どのくらいなんでしょうか。おそらく14ビットかもしれません。私の冷却CCDは古いですが、16ビットあります。たかだか2ビットの差ですが、4倍、測光では影響が出てくると思います。
ピクセルの大きさはため込む電荷の量や入ってくる光の量に関わるので、大きい方が感度いいし、飽和もしづらく階調も広くとれるでしょうか。解像度はやや落ちるのでしょうか、天体写真的なことはよくわかっていません。
ブルーミング(飽和)の問題、冷却カメラの仕様書には最近書かれていないことが多いです。撮像素子の最も大きな特徴は、直線的に電荷と光量の関係があることだと思います。強い光が当たれば、当然あふれ出しますが、本来はその状態を飽和と呼んでいましたが、今は、直線性を崩して、あふれ出ることを止めています。天体写真ではきれいに写っていいのですが、電荷を捨てる作業(画素にゲートを作って光を入れないようにしているのかな)をしています。直線性を崩すというのは、測光には致命的です。SOHOの画像で太陽のバックにある明るい星が飽和して横に電荷が流れ出ていたり、すばる望遠鏡の画像もそんなものがあったりします。あれはあれで、写っているものすべてが直線的に光量と比例している証拠です。
そんなこと言っていたら、NABG(ノンアンチブルーミング)以外のほとんどの素子が測光には不向きになってしまいます。そういう私の冷却CCDもブルーミング(飽和)を押さえる働きをします。
じゃあ、どうするかというと、電荷を捨て始める手前までを使っています。具体的には、機材にあった明るさの星を観測するとか、明るい星を観測する時は、ピントをぼかして1つの画素に入る光を分散させるとか、露光時間を調節するとか飽和させないような工夫をします。実際には勘と経験です。
でもそんなことして、いい加減なデータを報告すると叱られるので、測光の時に以下のようなことをしてどの程度の精度で測光できているのか調べておきます。

図は、測光で使うソフトの画面のひとつですが、左上のグラフ、画像に写っている星のほぼすべてがプロットされています。横軸は星の明るさ、縦軸は、測光値の標準偏差です。標準偏差が小さいところで測光している限り問題はありません。右側は暗い星で標準偏差は大きいですが、どの星も同じように標準編が大きいので、つまりばらつきは大きいけれど、平均値をとるとそれなりの光度曲線ができます。ところが、左の明るい星は、星によって標準偏差に違いがあり測光には向きません。適当に精度よく測光できるところに変光星や比較星を持っていくのが、先ほどの勘と経験です。帯状の分布から外れている星が変光星、または、変光が疑われる星です。
どこまで正しく理解できているかわかりませんが、測光には、まだ、いろいろな課題があったり、テクニック、知識が必要だったりで、終わりがありません。
ということで、カラー画像とモノクロ画像で違いが少しあるのですが、購入する機材と望遠鏡の組み合わせで、変光星の測光は可能と思います。画像の形式ですが、私は.ftsを使っています。他の形式の画像でも測光ソフトは動くようですが、使ったことがないので、なんともいえません。
--
☆☆☆彡
久保寺克明
m_akashi
 投稿数: 698
投稿数: 698
 投稿数: 698
投稿数: 698
要は、ダイナミックレンジと感度、ノイズ特性が良いことなどは、天体写真に求められる特性と同じですね。
あとは、受光量とデータ出力の間に線形性あるか?一眼デジカメは画像をRAWデータでも絵が破綻しないようにカメラが弄ってしまう機種もあるようですね。
購入したものは、ダイナミックレンジに関してはADコンバーターが16bit、出力されるファイルは14bitとのことで、階調
圧縮がかかってしまうのかもしれません。おそらくは、写真用のDataとして人減の認識できる階調としては14bitで十分という判断なんでしょうね。
デジタル一眼レフカメラで広範囲を撮影して、自動解析し変光星を含め突発的な増光を見つける手法とソフトも調べてみました。北海道の方がソフトを公開されていて、こういうのも面白そうです。
一眼レフカメラだとハードルがさがるので、このあたりから始めてみようかな。。。
余談ですが、日本人による超新星発見が多くなったのは、このソフトのおかげなのかなー。彗星探索に方がパンスターズ等の自動システムに敵わないと、超新星探索に転向したというのもあるようですが。
冷却CMOSは27日頃になりそうです。細かいものも揃えないといけないので、運用解しは2月になりそうです。
あとは、受光量とデータ出力の間に線形性あるか?一眼デジカメは画像をRAWデータでも絵が破綻しないようにカメラが弄ってしまう機種もあるようですね。
購入したものは、ダイナミックレンジに関してはADコンバーターが16bit、出力されるファイルは14bitとのことで、階調
圧縮がかかってしまうのかもしれません。おそらくは、写真用のDataとして人減の認識できる階調としては14bitで十分という判断なんでしょうね。
デジタル一眼レフカメラで広範囲を撮影して、自動解析し変光星を含め突発的な増光を見つける手法とソフトも調べてみました。北海道の方がソフトを公開されていて、こういうのも面白そうです。
一眼レフカメラだとハードルがさがるので、このあたりから始めてみようかな。。。
余談ですが、日本人による超新星発見が多くなったのは、このソフトのおかげなのかなー。彗星探索に方がパンスターズ等の自動システムに敵わないと、超新星探索に転向したというのもあるようですが。
冷却CMOSは27日頃になりそうです。細かいものも揃えないといけないので、運用解しは2月になりそうです。
k_kubotera
 投稿数: 4748
投稿数: 4748
 投稿数: 4748
投稿数: 4748
冷却CMOSの到着が近いということで、どんな画像が小田星ホームページに登場するか楽しみです。
それから、m_akashiさんの書き込みで、漠然と続けている変光星の観測に刺激がありました。いろいろと調べています。
変光星に限らず(いえできたら、変光星の観測にもそれだけの機材と知識とやる気を注いで)観測の方向に冷却CMOS使ってもらえたら、いいなと思います。
ダイナミックレンジの14ビットと16ビットの違いですが、測光にどのくらい影響するのか考えてみましたが、変わらないのかなと思います。16354階調と65536階調です。素人考えですが、6等星から16等星まで写っているとしてカウント値の範囲は、5000くらいです。14ビットでも16ビットでも階調の範囲内であれば変わらないです。よほどの露出オーバーでもしない限り問題ないです。1等星あたり500カウント、1カウントあたり0.002等です。実際は、明るい6等星から8等星くらいまでは飽和を起こしているでしょうからその半分の0.001等くらいの精度が出せるように思うのですが、どうでしょうか。普段の観測の値と誤差を見ても、そのあたりに限界があると感じます。空の状態で0.005等以内に誤差が収まる日は、冬ではほとんどありません。
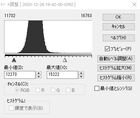
激変星、特に矮新星の観測は、m_akashiさんの調べた通りで、UGEM(ゆげむ、矮新星のふたご座Uから来ていると思います。)というソフトで監視しているようです。過去2週間くらいの観測報告を見ると、UGEMを使った報告をしているのは長崎の前田さんだけでした。たぶん、いろいろなノウハウを持っておられるのだと思います。データの不具合は、京都大学でされているですが、結構厳しくて、前田さんもはじめの頃、四苦八苦している様子がありました。今は、数十から多い日は1000以上の星をUGEMと自動導入で報告されています。今度メールしてお聞きしてみようと思います。とにかく矮新星の異常をいち早く見つけることが目的のひとつなので(長期にわたる光度観測も)、光度は小数第1位までです。異常が見つかればあとは、私たちのような一晩のんびり1つの星を追いかけるCCD組があとを引き継ぎます。前田さんだけでなく海外からのアラートもあるので、とてもじゃないですが、対応しきれません。
前田さんの報告には、
instruments: Nikon 300mm F4.5ED+Eos KissX3 exposure:30s
自動導入+撮影 ステラショット2.0
検出+測光 UGEM4
とありますから、m_akashiさんの設備で十分に対応できると思います。特に特別なフィルタも使っていませんし、普通の撮影機材と思います。
超新星の発見は日本が多いですね。東北の方がやっているのでしょうか。詳しいことはわからないですが、大型の望遠鏡で撮影、目で各銀河を確認していて、自動の検出ではないと思います。
海外では、ASASSNやZTFなど自動検出するシステムが動いています。そこで検出された星も観測することがあります。そんなプロの機材に近いことがアマチュアでもできてしまうのも、すごいですし、その追観測がアマチュアに振り向けられているというのも面白いです。
その他小惑星の自動検索などが彗星を見つけて、アマチュアの活躍場所を奪っていますよね。『彗星ニッポン』は、過去の話になりつつあるようですが、それでも日本人が彗星見つけます。『彗星ニッポン』は、生きていると思っています。関つとむさんの『未知の星を求めて』が復刻出版されますね。今、『彗星ニッポン』が蜂起する狼煙と思っています。
ASASSNなどの全天捜索のカメラにもかなり弱点があって、全天を見るがあまり、1つの場所をじっくり見ないので、短い周期の星や変光範囲の小さな変光星、たまにしか変光しない変光星、暗い変光星などは見落としています。まだまだ、アマチュアが活躍する場は、たくさんあります。
UGEMなども矮新星(1a型超新星の候補)を監視していますから、そこで捕らえた異常は大きな意味があります。とにかくプロの大型望遠鏡は、観測プログラムがいっぱいで、緊急なことてもない限り予定を変えませんから、私たちがゲリラ的に動き回ることは、とても楽しいです。小田星には、『戦う観測者』の血が流れていますから。
それから、m_akashiさんの書き込みで、漠然と続けている変光星の観測に刺激がありました。いろいろと調べています。
変光星に限らず(いえできたら、変光星の観測にもそれだけの機材と知識とやる気を注いで)観測の方向に冷却CMOS使ってもらえたら、いいなと思います。
ダイナミックレンジの14ビットと16ビットの違いですが、測光にどのくらい影響するのか考えてみましたが、変わらないのかなと思います。16354階調と65536階調です。素人考えですが、6等星から16等星まで写っているとしてカウント値の範囲は、5000くらいです。14ビットでも16ビットでも階調の範囲内であれば変わらないです。よほどの露出オーバーでもしない限り問題ないです。1等星あたり500カウント、1カウントあたり0.002等です。実際は、明るい6等星から8等星くらいまでは飽和を起こしているでしょうからその半分の0.001等くらいの精度が出せるように思うのですが、どうでしょうか。普段の観測の値と誤差を見ても、そのあたりに限界があると感じます。空の状態で0.005等以内に誤差が収まる日は、冬ではほとんどありません。
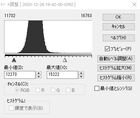
激変星、特に矮新星の観測は、m_akashiさんの調べた通りで、UGEM(ゆげむ、矮新星のふたご座Uから来ていると思います。)というソフトで監視しているようです。過去2週間くらいの観測報告を見ると、UGEMを使った報告をしているのは長崎の前田さんだけでした。たぶん、いろいろなノウハウを持っておられるのだと思います。データの不具合は、京都大学でされているですが、結構厳しくて、前田さんもはじめの頃、四苦八苦している様子がありました。今は、数十から多い日は1000以上の星をUGEMと自動導入で報告されています。今度メールしてお聞きしてみようと思います。とにかく矮新星の異常をいち早く見つけることが目的のひとつなので(長期にわたる光度観測も)、光度は小数第1位までです。異常が見つかればあとは、私たちのような一晩のんびり1つの星を追いかけるCCD組があとを引き継ぎます。前田さんだけでなく海外からのアラートもあるので、とてもじゃないですが、対応しきれません。
前田さんの報告には、
instruments: Nikon 300mm F4.5ED+Eos KissX3 exposure:30s
自動導入+撮影 ステラショット2.0
検出+測光 UGEM4
とありますから、m_akashiさんの設備で十分に対応できると思います。特に特別なフィルタも使っていませんし、普通の撮影機材と思います。
超新星の発見は日本が多いですね。東北の方がやっているのでしょうか。詳しいことはわからないですが、大型の望遠鏡で撮影、目で各銀河を確認していて、自動の検出ではないと思います。
海外では、ASASSNやZTFなど自動検出するシステムが動いています。そこで検出された星も観測することがあります。そんなプロの機材に近いことがアマチュアでもできてしまうのも、すごいですし、その追観測がアマチュアに振り向けられているというのも面白いです。
その他小惑星の自動検索などが彗星を見つけて、アマチュアの活躍場所を奪っていますよね。『彗星ニッポン』は、過去の話になりつつあるようですが、それでも日本人が彗星見つけます。『彗星ニッポン』は、生きていると思っています。関つとむさんの『未知の星を求めて』が復刻出版されますね。今、『彗星ニッポン』が蜂起する狼煙と思っています。
ASASSNなどの全天捜索のカメラにもかなり弱点があって、全天を見るがあまり、1つの場所をじっくり見ないので、短い周期の星や変光範囲の小さな変光星、たまにしか変光しない変光星、暗い変光星などは見落としています。まだまだ、アマチュアが活躍する場は、たくさんあります。
UGEMなども矮新星(1a型超新星の候補)を監視していますから、そこで捕らえた異常は大きな意味があります。とにかくプロの大型望遠鏡は、観測プログラムがいっぱいで、緊急なことてもない限り予定を変えませんから、私たちがゲリラ的に動き回ることは、とても楽しいです。小田星には、『戦う観測者』の血が流れていますから。
--
☆☆☆彡
久保寺克明
yomaiboshi
 投稿数: 273
投稿数: 273
 投稿数: 273
投稿数: 273
m_akashiさんも冷却CMOSを購入されたんですね。実は、昨日カラー冷却CMOSのQHY268Cが届きました。ただ、運用するためのRaspberry pi4のOSをUbuntu 21.04にしようとしているのですが、VNC組み込めず、難儀しています。冷却CMOSのことはよく分からない点がありますので、その節はよろしくお願いします。
nakanek
 投稿数: 3661
投稿数: 3661
 投稿数: 3661
投稿数: 3661
yomaiboshiさん
単なる興味ですがVNCを何に使うのですか?
winからRaspberry pi4をコントロールするため?
winからコントロールするだけねらxrdpがよさげです。
win標準のリモートデスクトップクラインとが使えます。
Raspberry pi4用のubuntuにパッケージが提供されているかは分かりませんが。。。
nakanek
単なる興味ですがVNCを何に使うのですか?
winからRaspberry pi4をコントロールするため?
winからコントロールするだけねらxrdpがよさげです。
win標準のリモートデスクトップクラインとが使えます。
Raspberry pi4用のubuntuにパッケージが提供されているかは分かりませんが。。。
nakanek
yomaiboshi
 投稿数: 273
投稿数: 273
 投稿数: 273
投稿数: 273
Raspberry Piをコントロールするのですが、Winではなく、Macbookです。子供のお古なんですが、充電がUSB-Cなので、バッテリーがアウトになっても、手軽に充電ができるんです。Macbookが手に入る前には、スマホでコントロールしていたので、その流れで今もVNCを使っているということです。
m_akashi
 投稿数: 698
投稿数: 698
 投稿数: 698
投稿数: 698
yomaiboshi さんはQHYのカラーにしましたか!私もQHYかASIかカラーにするかモノクロにするかかなり悩んで、ASIモノクロAPS 2600 MM Proにしました。センサーの基本設計は同じものですね。
結局ハッブルパレットで遊んでみたかったのと、カラーは改造一眼レフがあるので、という理由です。
とりあえず、中国から直接購入したオフアキが届きました。カメラはまだです。
結局ハッブルパレットで遊んでみたかったのと、カラーは改造一眼レフがあるので、という理由です。
とりあえず、中国から直接購入したオフアキが届きました。カメラはまだです。
nakanek
 投稿数: 3661
投稿数: 3661
 投稿数: 3661
投稿数: 3661
macですか・・・ちなみにwinからは大丈夫なのでしょうか?
ubuntu側か、mac側かの切り分けが必要だと。。。
nakanek
ubuntu側か、mac側かの切り分けが必要だと。。。
nakanek
yomaiboshi
 投稿数: 273
投稿数: 273
 投稿数: 273
投稿数: 273
akashiさん、私もQHYとASI、カラーとモノクロ、悩みました。年末にセールをしていたのですが、ASIは光害カットフィルターと併せた形でセールしており、QHYは本体だけで20%off+4千円のクーポン付きということもあり、QHYにしました。また、モノクロだとフィルターやフィルターホイールが必要になり、年金生活に片足を入れている身にとっては、ちょっと高価だし、その他諸々のことを考えカラーにしました。
早速、Raspberry Pi4 INDI systemに接続してみましたが、認識されませんでした。USBでは認識されているのですが。これから原因を探るのに時間がかかりそうです。
nakaneさん、winからも操作できます。Raspberry piの方の変更は一切なく、mac、win、ubuntu、Androidから操作できますよ。
早速、Raspberry Pi4 INDI systemに接続してみましたが、認識されませんでした。USBでは認識されているのですが。これから原因を探るのに時間がかかりそうです。
nakaneさん、winからも操作できます。Raspberry piの方の変更は一切なく、mac、win、ubuntu、Androidから操作できますよ。
m_akashi
 投稿数: 698
投稿数: 698
 投稿数: 698
投稿数: 698
私も年末セールに釣られました?。ただ、決めたのが遅くて、結局年末セールとは関係なく購入する結果です。
その分時間が取れたので、まあ、よかったかなと。
ワンョットカラーは効率が良いのが魅力ですよね。LRGBだと全データ撮影できないうち曇ってしまったなどということもありそです。彗星なんかは、動いてしまいますしね。
自宅からSHOな何日もにわたって露光とかするとかの楽しみ方ができそうということでモノクロにしました。もちろん、フィルターも買ったのでそれなりの投資です。これから、沢山撮影しないとですね。
その分時間が取れたので、まあ、よかったかなと。
ワンョットカラーは効率が良いのが魅力ですよね。LRGBだと全データ撮影できないうち曇ってしまったなどということもありそです。彗星なんかは、動いてしまいますしね。
自宅からSHOな何日もにわたって露光とかするとかの楽しみ方ができそうということでモノクロにしました。もちろん、フィルターも買ったのでそれなりの投資です。これから、沢山撮影しないとですね。

