おだほしぶろぐ - つれずれなるままにカテゴリのエントリ
今年は例年に無く暑い日が多いです。
9月も半ばになろうとしているのに今日もかるく30℃オーバー。
これだけ暑い日が続くと、ルーフ内の機材も心配になってきます。
・・かといって、小物は避難するも、固定した大物機材は
どうしようもありません。
そこで思いつきですが、キャンプ用の厚手のウレタン銀マットを
掛けてみました。
気温じたいは下がらないのでしょうが、屋根板からの輻射熱が
少しは遮られるためか、体感上は効果があるようです。
気温はこんなもん。
本来は熱室になっていいような条件なので、外(棒温度計)と
大差ないのでまあ良し、といったところです。
これをやったのは8月中旬。
銀マットは手元にあったので、もっと早く気づけばよかった。
sano

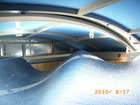


9月も半ばになろうとしているのに今日もかるく30℃オーバー。
これだけ暑い日が続くと、ルーフ内の機材も心配になってきます。
・・かといって、小物は避難するも、固定した大物機材は
どうしようもありません。
そこで思いつきですが、キャンプ用の厚手のウレタン銀マットを
掛けてみました。
気温じたいは下がらないのでしょうが、屋根板からの輻射熱が
少しは遮られるためか、体感上は効果があるようです。
気温はこんなもん。
本来は熱室になっていいような条件なので、外(棒温度計)と
大差ないのでまあ良し、といったところです。
これをやったのは8月中旬。
銀マットは手元にあったので、もっと早く気づけばよかった。
sano

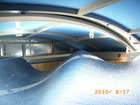


すごい雨でした。
本当に滝のような雨でした。
今日はたまたま休みを取っていて家にいたのですが、御殿場線止まっているし東海道も国府津?熱海間で運転見合わせ。会社に行っていたら家に帰れなかったです。
お昼前、郵便局に行くついでに酒匂川の橋(旧十文字橋)を渡ってみましたが、あと少しで河川敷まで届きそうでした。近くの会社の方か何台か車が止まっていたのですが慌てて車を移動する方がおられました。
数時間後、野次馬根性で同じ場所を通りましたがすでに河川敷は川となっていました。
今も東海道が止まっているのは酒匂川の増水の影響でしょう。
nakanek
本当に滝のような雨でした。
今日はたまたま休みを取っていて家にいたのですが、御殿場線止まっているし東海道も国府津?熱海間で運転見合わせ。会社に行っていたら家に帰れなかったです。
お昼前、郵便局に行くついでに酒匂川の橋(旧十文字橋)を渡ってみましたが、あと少しで河川敷まで届きそうでした。近くの会社の方か何台か車が止まっていたのですが慌てて車を移動する方がおられました。
数時間後、野次馬根性で同じ場所を通りましたがすでに河川敷は川となっていました。
今も東海道が止まっているのは酒匂川の増水の影響でしょう。
nakanek
暑いですね。
お盆休暇の間(私にはありませんでしたが)は、雲が多く
これで夏も終わりかとも思いましたが、そうはいかないよう
ですね。
今日のように大気温度が高く、陽射しが強いときに心配に
なるのが、スライドルーフ内の気温。
断熱材が付いているとは言っても僅かですし、基本的にアルミ板
1枚の屋根なので計画時点では自動車の車内のことなどを考え、
機材が高熱にさらされるのではないかと心配していました。
実際に作ってみると、写真のとおり心配したほどではありま
せんでした。
棒温度計はベランダの日陰で35℃、ルーフ内が37℃ですから
上出来だと思います。


今日は少し風通しをしていますが、閉めたままでも、今まで
40℃を越えたことはありません。
ルーフはニッシンドーム製です。
この断熱の程度も多すぎず少なすぎずで色々と経験から得られた
もののようです。
断熱材が多すぎると、そこが熱源になる事があるそうです。
少ないと電子機器がやられます。
なかなか一朝一夕ではないようです。
ちなみに、早川の自作ルーフは、木造でしかも断熱材をたっぷり
入れましたので断熱性能は良いです。
当時は断熱材が熱源となる事は考えてもいませんでしたが、
観察にも撮影にも支障はありませんでした。
拡大率が小さかったためかもしれません。
sano
お盆休暇の間(私にはありませんでしたが)は、雲が多く
これで夏も終わりかとも思いましたが、そうはいかないよう
ですね。
今日のように大気温度が高く、陽射しが強いときに心配に
なるのが、スライドルーフ内の気温。
断熱材が付いているとは言っても僅かですし、基本的にアルミ板
1枚の屋根なので計画時点では自動車の車内のことなどを考え、
機材が高熱にさらされるのではないかと心配していました。
実際に作ってみると、写真のとおり心配したほどではありま
せんでした。
棒温度計はベランダの日陰で35℃、ルーフ内が37℃ですから
上出来だと思います。


今日は少し風通しをしていますが、閉めたままでも、今まで
40℃を越えたことはありません。
ルーフはニッシンドーム製です。
この断熱の程度も多すぎず少なすぎずで色々と経験から得られた
もののようです。
断熱材が多すぎると、そこが熱源になる事があるそうです。
少ないと電子機器がやられます。
なかなか一朝一夕ではないようです。
ちなみに、早川の自作ルーフは、木造でしかも断熱材をたっぷり
入れましたので断熱性能は良いです。
当時は断熱材が熱源となる事は考えてもいませんでしたが、
観察にも撮影にも支障はありませんでした。
拡大率が小さかったためかもしれません。
sano
今年も夏の恒例行事、JAXA相模原キャンパスの公開に行きました。
展示物が大きく変わるわけではないのですが、今年ははやぶさ帰還の
関係もあり、しかも、隣の相模原博物館には帰還カプセルが展示されて
いるとあって大混雑。
いつになく早い出発(8時)の効果もあって、駐車場は何とかセーフ。
しかし会場内はかなりの人出。
カプセルの方は開場早々ですでに最後尾は宇宙研の中まで。

宇宙研のほうも人が多くて、満足に見学はできませんでした。
宇宙に興味を持つ人が多いのは嬉しいことですが、この状況は喜んで
良いものなのかな。


カプセルの列は、車道に出て交差点を跨いで博物館へとつながって
いました。
炎天の中ご苦労様です。
でも、そこまでしてもカプセルを見たい想いは見習いたいものです。
最近は、この感動や想いが失せてきているんですよね。
sano

展示物が大きく変わるわけではないのですが、今年ははやぶさ帰還の
関係もあり、しかも、隣の相模原博物館には帰還カプセルが展示されて
いるとあって大混雑。
いつになく早い出発(8時)の効果もあって、駐車場は何とかセーフ。
しかし会場内はかなりの人出。
カプセルの方は開場早々ですでに最後尾は宇宙研の中まで。

宇宙研のほうも人が多くて、満足に見学はできませんでした。
宇宙に興味を持つ人が多いのは嬉しいことですが、この状況は喜んで
良いものなのかな。


カプセルの列は、車道に出て交差点を跨いで博物館へとつながって
いました。
炎天の中ご苦労様です。
でも、そこまでしてもカプセルを見たい想いは見習いたいものです。
最近は、この感動や想いが失せてきているんですよね。
sano

先日、丹沢を歩いていたら突然何か大きな虫が腕に飛びついてきました。
びっくりして見たらオニヤンマでした。
すぐに逃げる様子も無かったので写真を撮りました。
こういうときコンデジは使えます。
何かくわえています。
どうも小さな蜂のようで、頭から喰いついています。
虫の世界ではこのような大型のトンボは脅威な虫なのでしょう。
観察していると、食いっぷりもバリバリと言った感じでした。
子供の頃は河川敷などに行くとこういったトンボも見かけましたが、
最近は見る事はありません。
徐々に環境は変わってきているのを実感します。
オニヤンマはしばらくつかまっていましたが、一瞬で飛び去りました。
あらためて近くで良く観ると見事な虫です。
目や羽根の構造や、素早い動きなど、すごいです。


びっくりして見たらオニヤンマでした。
すぐに逃げる様子も無かったので写真を撮りました。
こういうときコンデジは使えます。
何かくわえています。
どうも小さな蜂のようで、頭から喰いついています。
虫の世界ではこのような大型のトンボは脅威な虫なのでしょう。
観察していると、食いっぷりもバリバリと言った感じでした。
子供の頃は河川敷などに行くとこういったトンボも見かけましたが、
最近は見る事はありません。
徐々に環境は変わってきているのを実感します。
オニヤンマはしばらくつかまっていましたが、一瞬で飛び去りました。
あらためて近くで良く観ると見事な虫です。
目や羽根の構造や、素早い動きなど、すごいです。


大ガマのいた2010年7月現在の犬越路です。
ガマはこの下の山北側、竹やぶの中にいました。
聞くところによると、昔むかし(と言うほどではありませんが)
ここまでJP赤道儀を持ち上げた人たちがいたそうな・・。
確かに街明かりは少ないですが、展望も特に良いとは言えず、
その労力と困難さを考えると、とっても疑問です。(^^)
その想いと行動力は何だったのだろうか。
今となって考えると、その想いが行動を生み、前進の源になった
のだと思います。
少なからず自分にも覚えのあることなので、できるのならば
いまあのエネルギーがよみがえったらなんと嬉しいことか。
優れた機材や、それによる素晴らしい作品もいいですが、いちばん
大切なのは何なのか、改めて考えてしまいます。


ガマはこの下の山北側、竹やぶの中にいました。
聞くところによると、昔むかし(と言うほどではありませんが)
ここまでJP赤道儀を持ち上げた人たちがいたそうな・・。
確かに街明かりは少ないですが、展望も特に良いとは言えず、
その労力と困難さを考えると、とっても疑問です。(^^)
その想いと行動力は何だったのだろうか。
今となって考えると、その想いが行動を生み、前進の源になった
のだと思います。
少なからず自分にも覚えのあることなので、できるのならば
いまあのエネルギーがよみがえったらなんと嬉しいことか。
優れた機材や、それによる素晴らしい作品もいいですが、いちばん
大切なのは何なのか、改めて考えてしまいます。


先日、丹沢に行ったときに出会った「がま」です。
犬越路の下のところで、道の真ん中に行く手を阻むかのように
こちらに向かってどーんとすわっていました。
20cm位ある大きなかえるでした。


近づいても動じなく、かえるの王様の風格でユーモラスでした。
おたまじゃくしはどんなだったのだろうか、水溜りも無い山の
中でどこでどのように成長したのか、不思議です。

追記:
図鑑で調べたところ、この蛙は「アズマヒキガエル」のようです。
体長は50~150mmとありました。
手のひらを広げた位だったので20cm位あったのですが、いずれ
にしても大ガマだったようです。
おたまじゃくしでこの大きさになるのではなくて、早々に小さな
蛙になって冬眠もして徐々に成長するそうです。
・・とすると、この蛙は何歳くらいだったのでしょう。
山の主だったのかもしれないね。
お願い事をしておけばよかったかも。
犬越路の下のところで、道の真ん中に行く手を阻むかのように
こちらに向かってどーんとすわっていました。
20cm位ある大きなかえるでした。


近づいても動じなく、かえるの王様の風格でユーモラスでした。
おたまじゃくしはどんなだったのだろうか、水溜りも無い山の
中でどこでどのように成長したのか、不思議です。

追記:
図鑑で調べたところ、この蛙は「アズマヒキガエル」のようです。
体長は50~150mmとありました。
手のひらを広げた位だったので20cm位あったのですが、いずれ
にしても大ガマだったようです。
おたまじゃくしでこの大きさになるのではなくて、早々に小さな
蛙になって冬眠もして徐々に成長するそうです。
・・とすると、この蛙は何歳くらいだったのでしょう。
山の主だったのかもしれないね。
お願い事をしておけばよかったかも。

