追尾のずれが気になる!
- このフォーラムに新しいトピックを立てることはできません
- このフォーラムではゲスト投稿が禁止されています
投稿ツリー
-
 追尾のずれが気になる!
(k_kubotera, 2021/2/7 10:34)
追尾のずれが気になる!
(k_kubotera, 2021/2/7 10:34)
-
 Re: 追尾のずれが気になる!
(k_kubotera, 2021/2/8 7:28)
Re: 追尾のずれが気になる!
(k_kubotera, 2021/2/8 7:28)
k_kubotera
 投稿数: 4748
投稿数: 4748
 投稿数: 4748
投稿数: 4748
一昨日から赤道儀の動きにわすかなブレが出ていました。ASASSN-21auなど こぐま座で、北天の空の撮影に限ったことかなと思いましたが、試しに東のやや高度のある空で撮影してみました。明け方起き出して、5時過ぎの薄明の中撮影しました。
M13は、明るいです。5cmのファインダーで簡単に見つけられました。それで、90秒露出しました。
画像では、コンポジットしてわかりづらいですが、東西にガイドのずれがあります。北天の東側では、ほぼ南北にずれました。うーーーん。明るくなつてから調べ直してみましたら鏡筒バンドを取り付けるM8の六角ボルトが4つとも手で締めてあるだけの仮止め状態でした。たぶんこれかな。
次回撮影してみて同じ現象が出るようなら再検討です。
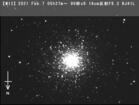
M13は、明るいです。5cmのファインダーで簡単に見つけられました。それで、90秒露出しました。
画像では、コンポジットしてわかりづらいですが、東西にガイドのずれがあります。北天の東側では、ほぼ南北にずれました。うーーーん。明るくなつてから調べ直してみましたら鏡筒バンドを取り付けるM8の六角ボルトが4つとも手で締めてあるだけの仮止め状態でした。たぶんこれかな。
次回撮影してみて同じ現象が出るようなら再検討です。
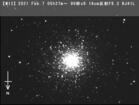
k_kubotera
 投稿数: 4748
投稿数: 4748
 投稿数: 4748
投稿数: 4748
やはり、鏡筒バンドのM8ネジの緩みが原因だったようで、追尾での異常は起きなくなりました。明け方、ASASSN-21auは、かすかに写るのですが、暗くて測光できる範囲ではありませんでした。
鏡筒の焦点距離を1330mmにしたので、赤道儀の追尾のチェックも兼ねて、おおぐま座周辺の有名どころのメシエ散歩をしました。
ピントは相変わらず変光星仕様です。ピントは、これ以上シャープにはならないかもしれません。筒内気流やシンチレーションで星像の直径がかなり変わります。今のところこれがベストなのかもしれません。ピントをいじると測光精度が落ちる可能性があるので、1度固定したら、あまり動かさないようにしています。冬は、シンチレーションが大きいのでピント合わせの季節ではありません。今回コマコレクターのレンズを入れたので焦点距離が伸びました。暗い星を精度よく測光するには、焦点距離を伸ばしてFを大きくして背景の空の明るさを少なくする必要があります。
メシエ散歩もいいですね。ちょっと寒かったですが、久しぶりにたくさん着込んで空(画面)を見ました。こと座のリング星雲も撮影したのですが、低空で薄明もあり、リングも明るいので画面が飽和気味になってしまいました。

M101、画面からはみ出してしまいそうです。はみ出ているかな。導入時は、うっすらとしか画面に出ないので、うまく画面内におさまりません。画面いっぱいに出て、おおっ!!って感じでした。

M51。超有名どころの銀河です。明るくてコントラストがあって,かつて印画紙で写真を焼きつけていた頃、天文台で撮影した画像をテスト用によく使いました。こんな写真が撮れたらいいなぁと思っていましたが、今では、アマチュアですらあまり撮影しないのかな。以前、超新星が出ましたが、どうやって測光したんだろう?背景は星間雲が明るいし,少なくとも、私の望遠鏡では測光できません。

M97、通称『ふくろう星雲』、確かにフクロウの顔に見えますが、CCDで撮像していると画面にはもっと広がりがあるように写って、濃淡があり耳のあるタヌキの顔にも見えました。

M109、棒状の渦巻き銀河です。天の川銀河も銀河同士の衝突でやや棒状と言われていますが、宇宙の壮大さ時間と空間と物質の不思議を感じさせます。
どの画像も、16cm f1330mm F8.3 BJ41L 露出90秒 5から8枚のコンポジットです。ビニングは2X2 冷却温度は-10Cです。観賞用の画像にするには、ビニングを1X1 冷却温度ももっと下げてノイズを減らしたりすると思います。
鏡筒の焦点距離を1330mmにしたので、赤道儀の追尾のチェックも兼ねて、おおぐま座周辺の有名どころのメシエ散歩をしました。
ピントは相変わらず変光星仕様です。ピントは、これ以上シャープにはならないかもしれません。筒内気流やシンチレーションで星像の直径がかなり変わります。今のところこれがベストなのかもしれません。ピントをいじると測光精度が落ちる可能性があるので、1度固定したら、あまり動かさないようにしています。冬は、シンチレーションが大きいのでピント合わせの季節ではありません。今回コマコレクターのレンズを入れたので焦点距離が伸びました。暗い星を精度よく測光するには、焦点距離を伸ばしてFを大きくして背景の空の明るさを少なくする必要があります。
メシエ散歩もいいですね。ちょっと寒かったですが、久しぶりにたくさん着込んで空(画面)を見ました。こと座のリング星雲も撮影したのですが、低空で薄明もあり、リングも明るいので画面が飽和気味になってしまいました。

M101、画面からはみ出してしまいそうです。はみ出ているかな。導入時は、うっすらとしか画面に出ないので、うまく画面内におさまりません。画面いっぱいに出て、おおっ!!って感じでした。

M51。超有名どころの銀河です。明るくてコントラストがあって,かつて印画紙で写真を焼きつけていた頃、天文台で撮影した画像をテスト用によく使いました。こんな写真が撮れたらいいなぁと思っていましたが、今では、アマチュアですらあまり撮影しないのかな。以前、超新星が出ましたが、どうやって測光したんだろう?背景は星間雲が明るいし,少なくとも、私の望遠鏡では測光できません。

M97、通称『ふくろう星雲』、確かにフクロウの顔に見えますが、CCDで撮像していると画面にはもっと広がりがあるように写って、濃淡があり耳のあるタヌキの顔にも見えました。

M109、棒状の渦巻き銀河です。天の川銀河も銀河同士の衝突でやや棒状と言われていますが、宇宙の壮大さ時間と空間と物質の不思議を感じさせます。
どの画像も、16cm f1330mm F8.3 BJ41L 露出90秒 5から8枚のコンポジットです。ビニングは2X2 冷却温度は-10Cです。観賞用の画像にするには、ビニングを1X1 冷却温度ももっと下げてノイズを減らしたりすると思います。
